contents
2014年8月 (10)
日本のファッション、美術と工芸を研究し、技術を習得したことが、舘鼻則孝の表現の礎をなしている。一方、フォトグラファーハルは、「東京に住んでいる自分だからこそ表現できることを見つけ、世界に発信していきたい」と創作のモチベーションについて語る。2人は『イメージメーカー展』から何を感じ、今後の展開へとつなげていくのだろうか? 2人の対談を取材した。

──お2人の作品が並ぶこの展示室を見たときの印象を教えてください。
ハル:世界を舞台にして、日本人としてどういう表現をしていくか、と考えて作品を制作している点が共通していると感じました。それと、身体表現ですね。私はカップルの身体を使って画面をつくっていますし、舘鼻さんも、下駄や靴の制作を通じて女性の姿をつくり出しているわけですから。
舘鼻:やはり日本人の表現ということが共通していますよね。ハルさんの作品からは日本のサブカルチャーが見えてくるといわれますが、私の表現もサブカルチャーに変わりありません。海外の文化が日本に入ってきて、それが昇華されて日本の文化として成り立っているということは、要するに伝統的な日本文化からしたらサブカルチャーと呼べますよね。
ハル:私はよく、アングラなカルチャーの世界で活動をしている作家だととらえられていることが多いですけど、今回の展示みたいに、キャリアも長く第一線で活躍されてきた方々と一緒に展示されたのは、自分としても貴重な経験でした。とはいうものの、人の身体や顔が写った写真を切り貼りするグードさんの手法なんかは、世界中にインパクトを与えてグードさんの表現として認識されていますけど、今広告などで使われたら、危険な表現だと受け取られないとも限りませんよね。だから、私の真空パックの作品も「よい子はマネしないでください」といわれるような表現ですが(笑)、エレーヌさんが抵抗なくラインナップしてくれたのかもしれません。
舘鼻:グードさんと会ったときには「キッズ」って呼ばれたんですよ。私は29歳だから、彼からしたら若造ということですよね(笑)。でも、そういうグードさんが回顧展のような形式で過去の作品から新作までを展示していて、その一方で、私やハルさんみたいな、グードさんにとっての「キッズ」の作品が一緒に展示されている。出展作家が少ないグループ展で、こういう年齢やタイプの違う作家が集まるケースはすごく珍しいし、ひとりひとりが違うタイムラインを持っていて、それぞれのストーリーが表現されている今回の企画はとてもおもしろいと思いましたね。展覧会ディレクターの手腕がすごいと純粋に感じました。
──作家のキャリアも表現するメディアも異なりながら、それぞれの表現に共通点が見えるのが『イメージメーカー展』のおもしろさのひとつだと感じました。
ハル:最近、広告の仕事として動画制作をする機会が増えてきているのですが、作品でも動画に挑戦したいと考えているんですね。パッと見て認識できるのが写真の大きな特徴のひとつで、映像はというと、見るためにある程度の積極性が要求されますよね。展覧会では、立ち止まってある程度時間をかける必要があるし、家で見るとしたら、再生しないと見られない。その違いは、表現としての特性の違いにも表れていると思うんです。写真で物語を感じさせ、起承転結を持たせるのだとしたら、それは映像を使ったほうがより伝わるかもしれない。今回、ロバート・ウィルソンさんのビデオポートレートを見たとき、本当にその中間をやっていると感じました。時間経過や動きを表現しつつ、写真のように画面のディテールもきちっと見せている。そういうのを感じられたのはとても興味深かったですね。
──グループ展として、いろいろなタイムラインや時代に応じた表現が見えたことと同時に、舘鼻さんという1人の作家の展示から、西洋と東洋、古典と現代といった要素の連続性と対比が見えてきたのも印象的でした。
舘鼻:自分が日本人のアイデンティティを持っていて、その上で現代的な表現を行うためには、日本の現代性というのがどういうところにあるのか、常に探し続ける必要があります。海外から入ってきた文化が日本で独自の進化を遂げて日本的になっているのも、日本人の編集能力の高さによるものだと思うし、その感性が日本の流行の移り変わりの早さとも結びついているはずです。そういう背景から生まれる最先端なものを海外の人にも伝え、理解してもらうためには、時代や文化的なつながりをきちんと説明する必要があります。ヒールレスシューズの裏付けとして日本の下駄があるわけですし、膝の上まであるレザーのブーツと西洋のルネサンス美術との関係を説明することもできますし、美術の歴史と、日本の歴史と、自分の思考過程とがどのように重なり合っているかを提示することが重要だと考えています。おそらく、今回の展示でその一端を表現することができたのかもしれません。
ハル:インターネットも進化して、過去にどのようなものがつくられていて、世界のどういう場所でどういう生活が行われているのか、などのさまざまな情報を手に入れられるようになりました。つまりある意味で、時代も場所も地ならしされてしまったわけです。写真に関していうと、現在はあらゆるものが撮りつくされてしまった感がありますよね。だからこそ、今まで誰もやっていなかったことをやることが一番大事で、今までに撮られたことのないイメージを見つけたときの驚きも喜びも、とてつもなく大きいと思っています。そして、時代も場所も地ならしされたこの状況を利用すれば、東京で生活しているから得られる感覚で制作した作品を、例えば東京に居ながらにしてニューヨークの人に見てもらうことができるわけです。グローバル化によって、時代や文化のすき間に生まれたローカルで個人的な表現をおもしろがってもらえる土壌が、現代にはあると感じています。

構成・文:中島良平
写真:木奥恵三
プロフィール/
舘鼻則孝:1985年、東京生まれ。15歳のときから独学で洋服や靴の制作を始める。東京藝術大学に進学して絵画や彫刻、染織などを学び、やがて花魁に関する研究に着手し、友禅染めを用いた着物や下駄を制作。2010年、自身のブランド「NORITAKA TATEHANA」を設立。全工程を手作業で完成させる靴が、LADY GAGAなどに愛用されていることでも知られている。
フォトグラファーハル:1971年、東京生まれ。東海大学工学部機械科卒業。2004年に写真集「PINKY & KILLER」発表後、カップルを被写体に撮影を行っている。2011年、2013年にニコンサロンで個展を開催し、海外のグループ展にも参加。写真集に「Pinky & Killer DX」「Couple Jam」「Flesh Love」ほか。並行して広告カメラマンとしても活動を行っている。
展覧会ディレクターのエレーヌ・ケルマシュターは、舘鼻則孝のことを「伝統と未来を見据えてものづくりを行う作家」と、フォトグラファーハルを「カップルをモデルにイメージをつくりあげ、"予想不能"なコンポジションに"愛"を表現するイメージメーカー」と表現する。『イメージメーカー展』では、ふたりの作品が同じ展示室に並べられた。前編と後編の2回にわたる今回のレポート。前編では、それぞれのコメントから2人の表現を紹介する。

展示室に足を踏み入れると、まず目に入ってくるのが石膏による足が林立するインスタレーション。かつて舘鼻則孝が、1枚の皮革から足のフォルムをかたどったブーツを手がけたことがあり、それを石膏で何足も複製することによってこのインスタレーションは生まれた。人の足の構造をリサーチする標本のようでもあり、また、ロダンなど西洋の近代彫刻家たちによる体のパーツの習作が集積した様子も連想させる。

ファッションデザイナーを目指すときにまず日本のファッションを勉強したという舘鼻は、「自分のルーツにあるのは日本のファッションへの関心であり、そこから展開する前衛的で新しいものづくりを追求している」と語る。「今回はほとんどが新作なんですが、ファッションアイテムである靴と、中庭のサンクンコートに展示されたかんざしがモチーフの大きな彫刻作品、その中間であるインスタレーションやオブジェ、という3つのセクションで構成しています。ここに展示したヒールレスシューズは、日本の下駄にインスパイアされて生まれた作品です。その関係性を見せるために、学生のころにつくり始めた下駄を展示しました。東洋の美術として生まれた日本の靴といえます。日本文化に西洋からの文化が影響を与え、融合することで現在の日本文化が生まれたわけですが、そのような西洋と東洋の対比や、古典と現代表現のつながりを常に意識しています」
足が地面よりも高いところに置かれる日本の下駄を工芸の技術によって洗練させた作品。そしてその対比として、伝統的な技術にインスパイアされ、東洋と西洋の融合を現代のモードに昇華したヒールレスシューズ。舘鼻は日本の花魁を研究することで着物や下駄の文化を知り、最新の表現へと展開させるために、ルネサンスや近代彫刻などの西洋芸術も学んだ。身にまとうものを手がけるために、身体性の研究にも余念がない。多様な表現を行いながら、根底にあるのはひとつの意識だということが展示から伝わってくる。
「日本の文化を世界の人に知ってもらいたい、というのが制作の大きな動機です。それをより現代的で新しい形で行うには、どのような技法や素材を用いるのがいいか。美術にも工芸にも歴史的な時間軸があるので、それを横並びで見て、重なり合う部分を説明しながら紐解いているのが自分にとっての制作活動であり、今回の展示でやりたかったことです」

舘鼻の作品と対面する形で、壁面にはフォトグラファーハルの写真作品が展示されている。色鮮やかな画面に写されているのは、布団圧縮袋に真空パックされたカップルの姿。「カップル2人の距離感がどれだけ近づいてひとつになることができるか、それを表現したい」と、ハルはこれまでのすべての作品に通じる制作動機について語る。「袋の上に寝転がってもらって、関節の位置や体のバランスなどを考えながらカップル2人と私との3人でディスカッションして構図を決めます。そのときに、私が俯瞰でそのフォルムが美しいかどうかを考えますし、実際に袋に入って掃除機で空気を抜くことで予期していなかった構図が生まれもします。1分か2分かけて徐々に空気が抜けていき、最終的に顔にピタッとビニールが貼り付いた時点で呼吸ができなくなるので、そこから10秒カウントダウンしながら、袋をグッと引っ張って服の細かいシワを直したり、腕や足の位置を動かしたりして、1回シャッターを切るわけです。そして、シャッターを切ったと同時に袋を開ける。息ができないので時間との勝負です。完璧にコントロールして同じ構図の真空状態をつくることは二度とできませんし、10秒間という限られた時間でその瞬間を画面に切り取ることに、写真というメディアを使う必然性があると思っています」
画面構成を想定し、カップルとの共同作業で被写体をつくりあげる作業が非常に重要な位置を占める。そうして生まれた作品から、新たにイメージが広がり次の作品のアイデアが生まれるという。圧倒的なインパクトを持つ画面は、その構図とディテールの結びつきによって見るものの目を釘付けにする。
「今回展示した7点のうち、1点は『Flesh Love』という2010年の作品で、もう6点は『Zatsuran』という2012年と2013年に撮影した作品です。カップルの2人と、彼らが普段使っているものや家にあるものを一緒に真空パックしています。2人の持ち物が2人に吸い寄せられた貼り付いている様子を撮影することで、 ふたりが引かれ合うパワーがより高次元で表現できると考えたわけです」
記事の後編では、それぞれが考える日本的な表現や、『イメージメーカー』という展覧会としての独自性などについて語った、舘鼻とハルの対談をレポートする。
構成・文:中島良平
写真:木奥恵三
プロフィール/
舘鼻則孝:1985年、東京生まれ。15歳のときから独学で洋服や靴の制作を始める。東京藝術大学に進学して絵画や彫刻、染織などを学び、やがて花魁に関する研究に着手し、友禅染めを用いた着物や下駄を制作。2010年、自身のブランド「NORITAKA TATEHANA」を設立。全工程を手作業で完成させる靴が、LADY GAGAなどに愛用されていることでも知られている。
フォトグラファーハル:1971年、東京生まれ。東海大学工学部機械科卒業。2004年に写真集「PINKY & KILLER」発表後、カップルを被写体に撮影を行っている。2011年、2013年にニコンサロンで個展を開催し、海外のグループ展にも参加。写真集に「Pinky & Killer DX」「Couple Jam」「Flesh Love」ほか。並行して広告カメラマンとしても活動を行っている。
開催中の企画展「イメージメーカー展」に関連して、本展参加作家 ジャン=ポール・グードのインタビューが、『Casa BRUTUS』9月号に掲載されました。

会場1階の受付カウンター脇に展示されたハンブルグの若き王子アレクシス・ブロシェクを撮影した作品に始まり、ロバート・ウィルソンのビデオポートレート作品は『イメージメーカー展』会場内に点在する。展覧会ディレクターのエレーヌ・ケルマシュターは、「通路や階段などを歩くたびに空間的な発見がある安藤忠雄さんの建築にオマージュを表し、展示空間を案内する役割を果たせるのと同時に出品作家たちそれぞれが持つ表現世界のリンクを見せようと考えた」と、キュレーションの意図を語る。設営のために来日したクリエイティブ・プロデューサーのマシュー・シャタックに、ビデオポートレートのプロジェクトについて話を聞いた。

「2004年に始まったビデオポートレートは、ファッションのイメージ映像やTVCMと、映画との中間といえるような形態で制作されます。セットに立ち会うスタッフは40人程度。カメラマンやエンジニア、スタイリスト、ヘアメイクなどのチームが集まって撮影が行われるのです。そのプロデュースを私どもの会社で手がけています」
舞台美術家として最初に知名度を高めたロバート・ウィルソンだが、キャリアの早い段階から複数のメディアでの表現をスタートしており、ビデオを使った作品制作の開始も1978年にさかのぼる。『Video 50』という、30秒ほどの映像スケッチを集めて51分ほどの尺に仕上げた作品だ。マシュー・シャタックは、ロバート・ウィルソンが70年代当時から豊かな映像的アイデアを持っていたことを強調する。
「ビデオポートレートのアイデアもずいぶんと以前から持っていましたが、そのアイデアを形にするためには、2000年代まで待つ必要がありました。技術的な問題です。ハイスピード映像も高精細で収録できるビデオカメラの技術、映像のデリケートなつなぎ目を処理できる編集技術、そして何よりもディスプレーの技術。ビデオポートレートの展示にはパナソニックのプラズマモニターを採用しているのですが、このモニターは、カメラでとらえた黒を"本物の黒"として再現してくれる。赤も同様です。そうした色は再現が難しく、以前のテレビ技術だと黒は濃いグレーに過ぎなかったし、赤も濃いオレンジだった。その技術進歩がなければ、ビデオポートレートはいつまでも実現することがなかったでしょう」

アレクシス・ブロシェクを被写体とする作品は、ステージと緞帳の背景に、スーツ姿で動物のマスクをかぶった姿がまず画面に映し出される。そして、マスクを脱いで現れるのは、11歳の少年の姿。作品は『イメージメーカー展』という異世界へと誘う導入装置となる。そして、歌手のマリアンヌ・フェイスフルや俳優のスティーブ・ブシェミ、中国人初のノーベル賞作家である高行健(ガオ・シンジェン)、ヤマアラシのボリスや犬のセリーヌ、モナコのカロリーヌ王女といったように、被写体がさまざまであるばかりか、演出方法もそのトーンも多様に制作された7点が展示されている。
「ウィルソンの表現の特徴のひとつは、時間の使い方にあるといえます。舞台作品においても、とても時間がゆっくりと流れる作品があります。早い時間の流れでは浮かび上がらない事実、気づくことのできない事柄と出会うことができる、という考えでそのように時間が使われているのです。ビデオポートレートも同様の考えで、基本的にゆっくりした時間が流れ、静かで、荘厳で、いくつもの意味のレイヤーがかかった作品として制作されています。しかし、ウィルソンは犬のセリーヌを用いて制作しているように、シリアスな作品を手がける一方で、コミカルで笑えるような作品も制作しています。多様なメディアで制作を行い、作品のトーンも均一化することなく制作を続ける。それがロバート・ウィルソンというアーティストの制作姿勢の大きな特徴だといえるでしょう」
構成・文:中島良平
写真:木奥恵三
プロフィール/
ロバート・ウィルソン:舞台美術家・演出家兼ヴィジュアル・アーティストとして世界で最も有名な人物の一人。ダンス、ムーブメント、照明、彫刻、音楽、テキストなど、さまざまな芸術媒体を自由に統合して表現を行う。アメリカ芸術文化アカデミーの会員であり、フランスの芸術文化勲章最高位の「コマンドゥール」を受章している。ニューヨーク州ウォーターミルにあるパフォーミング・アーツの実験ラボ、ウォーターミル・サンターの創立者兼芸術監督。
マシュー・シャタック:クリエイティブ・プロデューサー、Dissident Industries Inc. 創業者。ロバート・ウィルソンのビデオポートレート・シリーズのほかにも、ドキュメンタリー映画『カート・コバーン アバウト・ア・サン』『ビューティフル・ルーザーズ』、蔡國強のビデオインスタレーション作品『Fallen Blossoms』など、数々の映像プロジェクトのプロデュースに携わっている。
開催中の企画展「イメージメーカー展」に関連して、本展参加作家 ジャン=ポール・グードのインタビューが、『ソトコト』9月号に掲載されました。
また、ウェブサイトでもインタビューの一部が紹介されています。
>>『ソトコト』ウェブサイト

開催中の企画展「イメージメーカー展」に関連して、本展参加作家 ジャン=ポール・グードのインタビューが、『HARPER'S BAZAAR』(USA)8月号に掲載されました。

21_21 DESIGN SIGHTの地下1階に下りると、すぐ右手の壁面に展示されているのがデヴィッド・リンチのリトグラフ作品の数々だ。『マルホランド・ドライブ』や『インランド・エンパイア』といった作品で、現実と幻想のシームレスな世界を描ききった映画監督であり、音楽や絵画、写真などメディアを超えた表現活動を続けるデヴィッド・リンチについて、展覧会ディレクターのエレーヌ・ケルマシュターに話を聞いた。

2007年にパリのカルティエ現代美術財団で、デヴィッド・リンチの絵画、デッサン、写真、短編映像などを集めた大回顧展『The Air is on Fire』が開催された。そのときに彼が訪れたのが、モンパルナスのアトリエ「IDEM」。ピカソやマティスの作品も生み出されたこのアトリエでリンチはリトグラフに魅了され、毎年訪れて制作を行うようになったという。エレーヌ・ケルマシュターは次のように語る。
「リンチの表現に通底しているのは、夢のような幻想性を強烈なイメージに刻み付けている点。彼は映画監督として圧倒的に有名ですが、元々は画家を志していて素晴らしいドローイングを手がけます。映画においては音楽も自ら制作していて、すべてを結びつけて自分の世界を表現するイメージメーカーと呼ぶことができます。そして、常に実験を繰り返しています。リトグラフは彼にとって、石とインクを使用した実験だといえるでしょう。そうした実験と表現を通じて、彼は人間の内面世界へと導いてくれる。人々の見えざる内面をイメージとして描き出しているのです」
リンチが手がける作品では、ときとしてステージや緞帳が象徴的な役割を果たしている。異世界と日常空間をつなぐ装置として。今回、リンチの作品が壁面に並ぶ空間には、24点のリトグラフと対面する形でロバート・ウィルソンのビデオポートレイト作品も1点展示されている。彼もまた、舞台表現を通じて得た技術とインスピレーションをもとに、ビデオポートレイトという手法で人々の内面世界を浮かび上がらせている。そうした表現のリンクを発見することも、『イメージメーカー展』の楽しみのひとつだ。
構成・文:中島良平
写真:木奥恵三
プロフィール/
デヴィッド・リンチ:1946年モンタナ州生まれ。映画監督、脚本家、音楽家、画家、写真家、デザイナーとして活躍。『イレイザー・ヘッド』『エレファント・マン』といった初期作品がカルト映画として人気を集め、以後、『ブルーベルベット』や『ワイルド・アット・ハート』などスキャンダラスな表現を続ける。近年の『インランド・エンパイア』まで映画も制作する一方、分野を超えて作品を手がけており、日本では2012年にラフォーレミュージアム原宿でも個展が開催された。
開催中の企画展「イメージメーカー展」が、7/20発行の『SANKEI EXPRESS on the first Sunday』に掲載されました。

ジャン=ポール・グードの新作インスタレーションで音楽を担当したのが三宅 純。ジャズトランぺッターとして活動を開始し、1980年代より数々のCM音楽の作曲、2000年代以降はピナ・バウシュやフィリップ・ドゥクフレといった振付家の舞踏作品、またヴィム・ヴェンダースや大友克洋の映像作品に参加するなど、ジャンルを横断しながら生まれるサウンドの独自の響きが国際的に高い評価を受けている音楽家だ。2005年に拠点をパリに移したとき、最もコラボレーションをしてみたいと考えた作家のひとりがジャン=ポール・グードだった。そして初対面のとき、「ふたりとも丈の短いパンツだったからすぐに友だちになれたんですよ」と笑う。

「国境が地続きでいくつかの国と接していて、色々な場所に近くて移動しやすく、コラボレーションをしたいアーティストたちがたくさん通過する世界の"ハブ"のような街がいい」と考え、2005年に三宅 純はパリを拠点に選んだ。パリに移るとすぐに、思いがけずもグードから舞台作品の音楽をつくってもらえないかと相談を受けた。「彼にまつわる3人のミューズの舞台作品をつくりたい、と相談を受けたのが最初の出会いです。その作品は結局実現しなかったのですが、それ以来、彼に広告音楽を頼まれたり、私がアルバムジャケットのデザインをお願いしたり、ギャラリー・ラファイエットの広告に私が出たり、色々と交流があって、3年ほど前に今回のインスタレーションの話が出ました」
パリの装飾美術館で回顧展を終えたグードは、そこに展示したファリーダをモデルとする巨大な立体作品を動くインスタレーションにしたいと考え、三宅に相談をした。三面鏡のような装置を前にして回転するフィギュアが、無限にその像を増殖させていくようなアイデアなどをグードが語り、三宅はイメージを膨らませた。そして、ふとした雑談の内容が、最も三宅をインスパイアしたという。
「ジャン=ポールがファリーダと付き合っていたときに、一緒に飛行機に乗ってアラビア文字が書かれた彼女の写真を見ていたら、"私の父親はモロッコの音楽界の重鎮なんだ"と、隣の乗客が話しかけてきたそうなんです。その人はユダヤ系だったようで、"お前はワルツというものを知っているか? あれはユダヤ人がつくったんだぞ"という話を始めたのだと。ユダヤの民族はいろんな国に居住しているので、いろんな音楽のスタイルにあわせて変化しながら独自の表現をつくる、非常に音楽的才能のある人たちだと私は常々思っていて、ジャン=ポールの話を自然なこととして納得しました。単なる雑談のひとつだったんですが、それをきっかけに私はその歴史の流れを感じられるような音楽をイメージしました。ワルツが発展していった過程、もしくは、血が混じっていった過程を音楽にしたらどうかなと思ったのが最初だったのです」

ジャズトランぺッターとして活動を始めた三宅は、やがて、作曲家としてジャズの領域に留まらない活躍を続けることになる。「ジャズの場合はテーマがあってアドリブをするけど、他の人がソロ演奏をしているときに暇なんですよ」と冗談めいた話から、作曲活動のきっかけを語る。
「最初はトランペットを吹くことがモチベーションだったわけですが、ライブを続けるうちに、サウンド全体への興味が大きくなりました。それが高じて色々な曲を書くようになったんですが、トランペットだとジャズというカテゴリーに留まっていたのに、サウンド全体を考えるとそこから大きく逸脱できることに悦びを覚えました。演奏することはもちろんとてつもなく魅力的です。しかし当事者になると、全体が見えないジレンマがあります。逆に全体を見ようとすると、当然演奏には参加できません。だからときどきその両方をやるわけです」

さまざまな分野で音楽を手がけ続ける三宅が、初めて舞台作品を手がけたのが奇しくもロバート・ウィルソンの作品だった。その体験は三宅の以後の創作活動にとても大きな影響を与えた。
「各国からいろんなアーティストやスタッフが集まって、ひとつの目的に向かってチームで走るというのが、ミュージシャンとして活動してきたなかであまりなかった光景で、とても美しいものだと感じました。劇場の舞台袖や緞帳裏でストレッチをしているダンサーがいたり、楽屋に緊張感あふれる役者がいたり、そういう風景も含めて劇場は素敵だと思ったんです。そこにはたくさんの記憶が自然と宿っている気もしました。あとは、デヴィッド・リンチの『マルホランド・ドライブ』に出てくる"シレンシオ"という不思議な劇場にも衝撃を受けました。口パクで謎のパフォーマンスが行われている劇場で、観客はそのパフォーマンスの滑稽さを理解していながら、偽らざる涙を流しているんです。光景として、まさにあんなことが起こるような劇場をつくってみたかったんです」
2013年にリリースされたアルバム『Lost Memory Theatre act-1』は、失われた記憶への思いが音楽で表現された作品だ。これまでにもコラボレーションを行ってきた演出家の白井 晃がこの作品に惚れ込み、舞台化した作品を8月21日から31日まで神奈川芸術劇場(KAAT)で上演する。そこで生まれる音楽と舞台作品の新たな関係にも期待が高まる。
「私は言葉にできない心象風景や心情のレイヤーを音楽にしてきました。たったひとつの音だけで千の言葉以上のものを伝えられる事もある。そして、音楽体験には現実にはない時間が流れる瞬間もあると考えます。なぜ自分が音楽をしているかというと、言葉にできない心象風景や心の動きをレイヤーにして、ひとつの音でも何も語らずに何かを伝えられる、そして、音楽体験によって現実ではない時間が流れる場合もあると考えているからです。音楽の様式だけを考えると、もう飽和してからかなり長いというか、どのジャンルも一応飽和点まで行って重箱の隅をつついている状態です。その異種交配というか、すべてのジャンル様式を横断しながら表現するなかに日本人としてのアイデンティティが出てくるかもしれないし、もしかしたら、新しいオリジナルなものが創りだせるかもしれない。新しいものだけを目指すというよりも、過去の宝に封じ込められたものを掘り起こしつつ、それをいかに自分なりに展開させられるかというのが私のライフワークなのかもしれません」
構成・文:中島良平
写真:木奥恵三
プロフィール/
三宅 純:作曲家。日野皓正に見出され、バークリー音楽大学に学ぶ。ジャズトランぺッターとして活動開始後、ジャンルにとらわれない独自のスタイルで作曲家としても頭角を現す。CM、映画、アニメ、ドキュメンタリー、コンテンポラリーダンスなど多くの作品に関わり、カンヌ国際広告映画祭など受賞歴も多数。ピナ・バウシュ、ヴィム・ヴェンダース、ロバート・ウィルソン、オリバー・ストーン、大友克洋など、多くの表現者たちとコラボレート作品を残している。
2014年8月2日、映像作家・脚本家・写真家・作詞家の菱川勢一を招き、トーク「イメージを生み出す」を開催しました。

あらゆるフィールドを跨ぎ、既成の枠組みにとらわれることのない作家として知られる菱川。それは、既存の表現方法や分野を超えた自由な創造を行なう作家が集う本展と相通じます。トーク序盤では自身が歩んできた道について述べられました。菱川は高校卒業後放浪し、レコード会社を経てニューヨークに渡ったのち、映像からデザインの世界に入り、帰国後友人たちと共にグラフィックと映像を手がけるデザインスタジオ DRAWING AND MANUALを設立。そこで菱川は「モーショングラフィックス」と呼ばれる表現で名を知られるようになりました。次いで彼のデザインスタジオの話となり、手がけてきた作品の数々を映像トレーラーで紹介し、いくつか象徴的な作品の話に移りました。
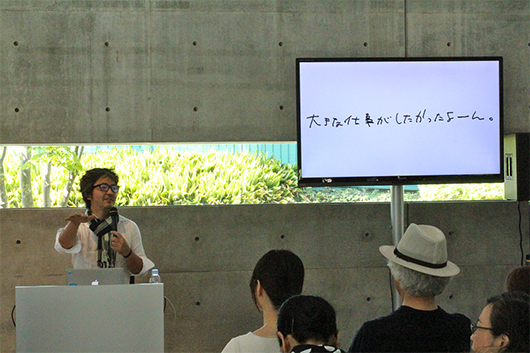
誰もが知っている大きな仕事という枠と「大衆」というテーマについて、「見てくださる、楽しんでくださる人々が多様であるということ」の難しさに触れながら、NTTドコモのCM「森の木琴 - Xylophone」では、全長44mに及ぶ木琴を用い、球が木琴を転がる様をワンテイクで収めるべく50回撮ったというエピソードに始まり、国宝をアニメーション化したというNHK大河ドラマ「功名が辻」でのオープニング映像や、同局スペシャルドラマ「坂の上の雲」や同局大河ドラマ「八重の桜」などの制作背景に及びました。「名前や体裁に拘らず、やりたいことがあれば今すぐやる。いい作品にはいいエピソードが残る」と菱川は結び、会場はダイナミックなイメージが生まれる現場となりました。
