contents
2月17日からスタートする企画展「アスリート展」。そのディレクター鼎談の第2回目を更新。「新豊洲 Brillia ランニングスタジアム」にて実施された為末によるランニング講座で汗を流した直後に、アスリートが得る喜びの本質とは何かについて迫りました。
(構成・文:村松 亮)
アスリートが体感する
本能的な喜びとは
緒方:アスリートには大なり小なり、大一番というのがありますよね。それがトップアスリートとなれば、4年に1回となって、その一瞬で過ぎ去ってしまうピークに対してコンディションを整え、トレーニングを重ねていく。大歓声に包まれて、競う相手がいて、時間の制約もあって、もっとも意識しなくてはならない本番の場面で、今度はいかに無意識になって、いつも通りの力を発揮できるかという(笑)。
 2017年1月、新豊洲Brilliaランニングスタジアムにて
2017年1月、新豊洲Brilliaランニングスタジアムにてーー意識的な場面でいかに無意識でやるか、と。
為末:おっしゃる通り、そんなことが実際にオリンピックや世界大会になるとあるんですね。アスリートが日々行っているトレーニングとは、意図して何かをやろうとして、うまくいったかの判定基準を振り返り、何がその結果に影響したのかを考えながら、また新しいものを試していく。そんなサイクルだと思うんです。身体の方は比較的にビデオなどもあってわかりやすいんですけど、それが心の世界となると、突然わかりづらくなります。「なんか力が出せなかった気がする」そんな曖昧な心理を振り返って、スタート前にどんな心の状態だったのかを考える。結局、掴めないで引退してしまう選手も少なくないかもしれません。掴めている選手であれば、どうもこういう風に入るとうまくいく、それを分かっていますから。正しい力を出せる心の状態があるかというと、そういうことでもないんです。
緒方:自分を知る、それ自体に長けているんでしょうね。
菅:アスリートにとっては、自己記録が出たときと、自分の身体を思った通りにコントロールできたとき、どちらの喜びが大きいんでしょうか。
為末:つまらない答えになりますけど、それもタイプによりますね。面白いのは、すごく勝ちたい。なんでもいいから勝ちたいという選手は、やっぱり勝つ。一方で勝ち負け以前に、自分自身がどこまでいけるのか、そういうことにこそ興味を持っていて自分をコントロールすることに喜びを得ている選手もいますから。そして僕が思う、アスリートが最も体感している原始的な喜びとは、"連動感"だと思うんです。例えば、駅のホームでおじさんが傘でゴルフのスウィングをしますよね? ピタっと一連の動作がハマると快感だったりします。できなかったことができるようになる瞬間もそうですし、何かこうしっくりきたときに感じる、生き物としての純粋な喜びみたいなもの。究極、みながそれを求めていくのではないかって思うんです。
菅:そうした原始的な喜びがないと、何事も続けられないですよね。そもそも本能的な喜びがベースにあって、だんだん喜び自体が、競争による勝ち負けといったような社会性を帯びていくわけですが、きっとその先には、また徐々に本能的な喜びにシフトしていくときがくるんでしょうね。
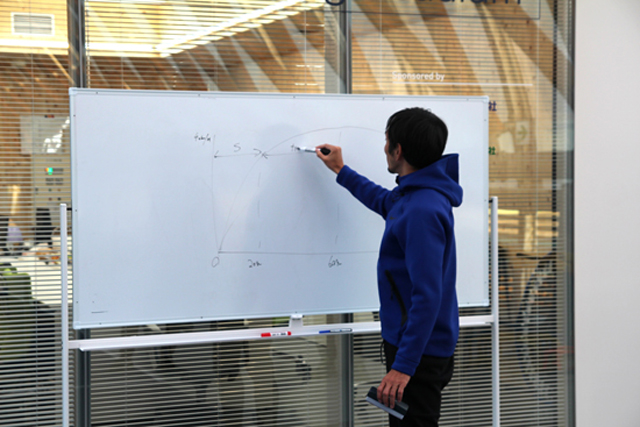 2017年1月、新豊洲Brilliaランニングスタジアムにて
2017年1月、新豊洲Brilliaランニングスタジアムにてディレクターズ紹介 2

おがた ひさと:
東京大学工学部産業機械工学科卒業。岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー(IAMAS)、LEADING EDGE DESIGNを経て、2012年よりTakramに参加。ハードウェア、ソフトウェアを問わず、デザイン、エンジニアリング、アート、サイエンスなど、領域横断的な活動を行う。主な受賞に、2004年グッドデザイン賞、2005年ドイツiFデザイン賞、2012年文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品、2015年グッドデザイン賞特別賞など。21_21 DESIGN SIGHT では企画展「骨展」「"これも自分と認めざるえない"展」「デザインあ展」に参加作家として出展。
